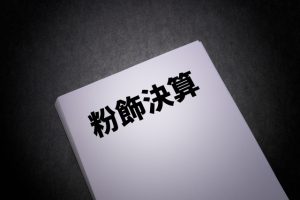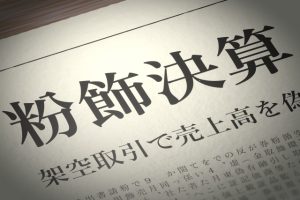ブログ
会社法の会計監査、平均監査報酬の動向と前期比較分析【監査実施状況調査2024年度】
今回は、監査実施状況調査2024年度が日本公認会計士協会(JICPA)より12月23日に公表されたことを受け、会社法監査に焦点を当て前期の平均監査報酬と比較し監査報酬の直近の動向についてご紹介します。
2026年度に「年収の壁」160万円から178万円へ!与党税制改正大綱決定へ
今回は、自民党と日本維新の会は19日、2026年度の与党税制改正大綱を決定する。所得税の課税最低限「年収の壁」を160万円から178万円に引き上げるなど家計支援が並んでいます。住宅ローン減税の限度額引き上げや、少額投資非課税制度(NISA)の拡充なども盛り込んだ事についてご紹介します。
オルツの不正会計 東証が会計監査人交代時は前任者への経緯等確認などの再発防止策を公表
今回は、東京証券取引所が12月9日に開催した「第5回IPO連携会議」にて、上場準備期間に会計監査人(監査法人)や主幹事証券会社が交代した場合に、取引所が前任者に交代経緯等を確認するなどの再発防止策を示した事についてご紹介します。
少額リース資産、会社の規模によっては300万円超でも対象になる?!
今回は、新リース会計基準では、少額リースに該当する場合、リース開始日に使用権資産とリース負債を計上しないことができます。実務上、少額リースの金額の基準や判定に含める金額、判定する時点などの疑問点についてご紹介します。
マイカー通期非課税限度額引き上げ、本年年調対応も!
今回は、マイカー通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が11月19日に交付されました。国税庁は同日、通勤手上の非課税減額の引上げに関するQ&A・パンフレット・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例を公表しました。施行日は11月20日です。当該改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及適用されることから、改正前の非課税限度額を超過した通勤手当を支払っている場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となる事についてご紹介します。
オルツの不正会計の概要と結末、IPOへの東証の対応について
今回は、AI開発ベンチャーの株式会社オルツが2025年に発覚した大規模な不正会計事件により、上場からわずか10ヶ月で上場廃止となり、2025年7月30日に民事再生法の適用を申請し、上場廃止となった問題とこの問題を受けて東京証券取引所が会計不正の早期発覚・未然防止について協議している事についてご紹介します。
ニデックの監査報告書「意見不表明」で、上場廃止の可能性も
今回は、ニデックの会計処理問題が長期化しており、不適切な会計処理の疑いを受け、監査を担当するPwCジャパンが9月26日、同社の2025年3月期の有価証券報告書(有報)に対して「意見不表明」を突きつけた事、および東京証券取引所が10月28日、ニデック株式を特別注意銘柄に指定した事についてご紹介します。
令和7年度税制改正の概要(物価上昇局面への対応)
今回は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として
•デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという所得税の課題に対応
•源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用
上記についてご紹介します。